去年の8月中頃迄は、自分の事は全て私の手を取る事なく炊事、洗濯出来ていた母(85歳)
自動車の免許も所有し、10月の病院入院迄は運転も出来ていた母。
母は色々持病(高血圧、心不全、脂肪肝、貧血)はあったのですが、介護保険は払うばかりで、申請すらしませんでした。
自分で市役所に行って相談したこともあると、言ってましたが、「車の免許を持っていてしっかりいているので申請できないと言われた、介護保険は使わないで死んでいったら、介護保険はなんにもならんねぇ」等言っていたこともありました。
そんな母が、10月入院!
入院後状態は不安定な状態でしたが、そんなに慌てて申請する事もないかと、近くの支所に相談すると、ディサービスの利用は、本人が行きたくないと、いう場合もあるので……等も窓口で言われたので断念しました。
それから、11月に入り入院生活が続く中、(せん妄)状態は悪化するばかり、環境の変化が一番の原因だろうとういう事で、自宅に帰ると何もなかった様に元に戻る人もいるとの事で、退院に向け試験外泊。
外泊当日、朝から迎えに行くと、身の回りの荷物を全てバラバラにバックにぐちゃぐちゃに入れてあり、その状態に言葉がでず、涙がこみああげてきました。
結局一泊の外泊は、母にとって(せん妄)を、より一層悪化させるものでした。
その2日後、また外泊をし、そのまま退院。
外泊中、とても母独り自宅に置き仕事に行くことは難しいと考え暫く、休職をすることを決意!
結局、介護申請(11月上旬)をして、介護の認定調査(12月初め)があり認定書が届く(12/20)まで、1ヶ月半程かかり、デイサービスを選んで、お試し利用(1/9)体験後の契約(1/15)まで数週間掛かったので結構時間を要しました。
母が入院した頃、早く介護申請していた方が良いよとは聞いていたけれど、こんなにも時間がかかるとは思ってませんでした。
なので、今回の経験を元に、実際に手順や介護保険の仕組みやサービスの利用方法を理解したうえで、困っている方、介護保険をスムーズに進めるための方法を書いてます。
介護保険しくみ
保険料の支払い開始年齢
【介護保険制度】は、2000年(平成12年)にスタートしました。
本格的に高齢化社会を迎える日本において、高齢者の暮らしや健康、安全を保証していこうという理念の元誕生した制度で、加入は40歳以上は全員保険者となり、介護サービスが受けられる高齢者になったとしても、死亡するまで保険料は払い続けます。
労働者が毎月受け取る給料からは、満40歳を迎えた国民は介護保険料を徴収されます。
介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営され、介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分類されています。
①第1号保険者(65歳以上)
第1被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となった時、市区町村の認定をうけ、サービスを利用できます。
※65歳以上の人で交通事故など第三者による、不法行為により介護保険を利用する場合は、市区町村への届け出が必要です。
②第2号保険者(40歳以上65歳未満)
労働者が毎月受け取る給料からは、満40歳を迎えた国民は「介護保険料」も徴収されることになります。
これは高齢者が介護サービスを受ける際に発生する費用に充てられ、高齢者の暮らしを支えていくための貴重な財源となるのです。
※特定疾病により、介護や支援が必要となった時、市区町村の認定をうけ、サービスが利用できます。
特定疾病(加齢と関係があり要支援、要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病)
| がん(医師が一般に認められている医学的知見の基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断されたものに限る) | 脊柱管狭窄症 |
| 関節リュウマチ | 早老症 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 多系統萎縮症 |
| 後縦靭帯骨化症 | 糖尿病精神障害.糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 脳血管疾患 |
| 初老期における認知症 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 進行性格上性麻痺.大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 脊髄小脳変性症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変性関節症 |
介護保険料
保険料が決めかたと納め方
第1号被保険者
65歳以上の人の保険料は市区町村で介護保険サービスに必要な費用などから算出された【基準額】を元に所得におおじて決まります。
各自治体が設定した「基準額」によって9段階に分類され、所得の多さや課税の有無、生活保護の受給状態などによって金額が決まります。当然、各自治体によって財源や被保険者数も変わってくるため、住まいのある地域によって保険料は変動します。
※市区町村によって必要となるサービス料や65歳以上の人数が異なるため基準額も異なります。

第2号被保険者
①職場の医療保険に加入している人の場合
第2号被保険者で社会保険加入者の場合、医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に介護保険料率を掛けた金額が算出され、その額を事業主と折半する形で決定します。
※この介護保険料率は各健康保険組合によって異なり、会社の規模や従業員数などによって差があります。
②国民健康保険加入者の場合
所得割(第2号保険者の所得に応じて計算)均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)、平等割(第2号被保険者の属する世帯で一世帯につきいくらと計算)を組み合わせて算出しますが、算定金額の項目および掛け率は自治体ごとによって異なります。
なお所得割に関しては、前年度の所得が反映されます。
保険料の納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって2種類に分けられます。
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から原則年金として納められます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人→年金から差し引き
年金の定期支払い(年6回)の際年金から保険料があらかじめ差し引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
◉前年度からから継続して特別徴収で保険料を納めている人は4.6.8月は仮に算定された保険料を納め、10.12.2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めまますので、保険料が変わることがあります。
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 年金
支給月 | 4月
(第1期) | 6月
(第2期) | 8月
(第3期) | 10月
(第4期) | 12月
(第5期) | 2月
(第6期) |
年金が年額18万以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
●年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
●他の市区町村から転入した場合
●年度途中で年金《老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金》の受給が始まった場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更があった場合
●年金が一時差し止めになった場合
普通徴収
年金が年額18万円未満の人→納付書.口座振替
市区町村から送付されてくる納付書や口座振替で期日までに金融機関などを通して保険料を納めます。
| 7月
(第1期) | 8月
(第2期) | 9月
(第3期) | 10月
(第4期) | 11月
(第5期) | 12月
(第6期) | 1月
(第7期) | 3月
(第8期) |
介護サービスの利用するまでの流れ
サービスも色々種類がありますが、どんなサービスを受けたいのか、決まってなくても、まずは地域包括支援センターや市区町村の窓口の相談しましょう。
①相談します
地域包括支援センターや、市区町村の窓口で、介護保険のサービスや介護予防、生活支援サービス事業所に、どんなサービスを受けたいのか相談します。
②申請
介護保険サービスの利用を希望する人は、まず市区町村の窓口に認定の申請をして下さい。
申請する人は、本人または家族などの他、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
③認定調査
市区町村の職員などが自宅へ訪問し、心身の状況などを調べるため、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)
認定調査を受けるときのポイント
●体調のよいとき(通常時)に調査を
いつもと違う体調の時では、正しい調査ができないことがあります。
●困っていることはメモしておく
緊張などから状況が伝えきれないこともあるので事前にメモしておくことをお勧めします。
●家族などに同席してもらう
家族などいつもの介護者に同席してもらえば、より正確な調査ができます。
●日常の補装具があれば伝える
杖など日常的に使っている補装具がある場合使用状態を伝えます。
※主治医意見書が必要となり、本人の主治医から介護を必要とする原因疾患についての記載を受けます。主治医がいない人は市区町村の指定した医師の診断が必要です。
主な調査項目
| 麻痺の有無 | 視力 | 意思の伝達 |
| 拘縮の有無 | 聴力 | 記憶・理解 |
| 寝返り | 移乗 | 大声を出す |
| 起き上がり | 嚥下 | ひどい物忘れ |
| 座位保持 | 食事摂取 | 薬の内服 |
| 両足での立位保持 | 排尿 | 金銭の管理 |
| 歩行 | 排便 | 日常の意志決意 |
| 立ち上がり | 清潔 | 過去14日間に受けた医療 |
| 片足での立位 | 衣類着脱 | 日常生活自立度 |
| 洗身 | 外出頻度 |
④審査.判定
一次判定(コンピューター判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、【介護認定審査会】で審査し要介護区分が判定されます。
⑤認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。
◎要介護1~5→介護サービスの利用ができます
◎要支援1・2→介護予防サービスと、市区町村が行う介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
◎非該当→介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
ただし基本チェックリストを受けて【介護予防・生活支援サービス業対象者】と認定される場合は、市区町村が行う介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
※認定結果の有効期限と更新の手続き
認定の有効期限は原則として新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です(月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+有効期間)。
また認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)
要介護・要支援認定は有効期間満了前に更新の手続きが秘湯用です
更新の申請は要介護認定の有効期間満了日の60日前から受付されます。
介護サービスの利用の仕方
【要介護1~5】と認定された人は、介護サービスを利用できます。居宅介護支援事業所などに依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
※サービス利用の相談は無料です。
ケアマネージャーが利用にあった【ケアプラン】を作成しプランに沿って、安心してサービスを利用できるよう支援します。
ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者の負担はなく安心です。
ここでは、在宅と、施設のサービスの利用の仕方を説明します。
在宅でサービスを利用したい
1.ケアプランの作成依頼
依頼する居宅介護支援事業者が決まったら市区町村《ケアプラン作成依頼届出書》を提出
2.ケアプランの作成
①利用者の現状を把握
ケアマネージャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
②サービス事業者との話し合い
利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
③ケアプランの作成
作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
3.サービス事業者との契約
4.在宅サービスの利用
施設に入所したい
1.介護保険施設と契約
入所を希望する施設に直接申し込みます。
居宅介護支援事業者などに紹介をしてもらうことも可能
2.ケアプランの作成
入所した施設で、ケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。
3.施設サービスを利用
最新情報をお届けします
Twitter でRurikahimeをフォローしよう!
Follow @rurikahime83





















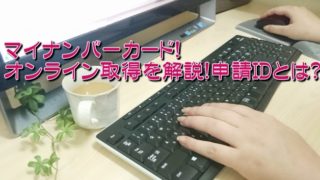














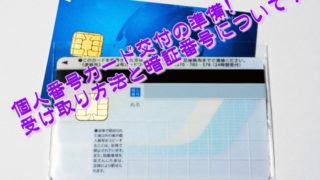
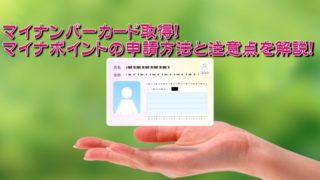











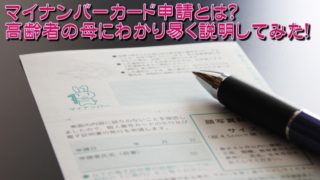




























♡コメント♡ コメントを書き込む♡