母(85歳)の認知症と心房細動で介護が急に必要になった事で、私は去年(令和元年)11月末から仕事を休職し、12月付で看護師の仕事を辞めました。
正式に退職の手続きの為、会社に行ったのは、1月になってからです。
その頃の母の状態は、振り返ると最悪の状態で、昼間起きているときは勿論、一時も目を離すことができず、夜になり一度目が覚めると、【せん妄】により、寝てくれない事もしばしばある状態でした。
そんな状態だったので、母を誰かに見てもらわないと、外出もできない、また預けるとなると、相手の都合も考えないといけなくて、やっと今年の1月に入り、叔父の家に母を預けて、病院へ退職の手続きに行きました。
それから、離職票が届いたころ、母は週2回のデイサービス利用を開始、その日を利用し【ハローワーク】に行きましたが、積極的な求職活動はできる状態ではなかったので、手続きは見送りました。
3月に入り、母の介護状態が、良いほうへ落ち着き再度、ハローワークへ。
失業保険【求職者給付】の受給は以前手続きをした事はあり、【自己都合退職】でしたが、すぐに就職先を探して、最短で再就職手もらえた経験もあります。
雇用保険制度も理解はしているつもりですが、今回は、母の介護による離職なので、【特定理由離職者】に当てはまり、会社都合と同様に優遇措置を受けられ、求職者給付の受給中です。
第1回の認定日の【雇用保険説明会】が、現在【コロナウィルス】の影響で、書面での説明でした。
また数回ハローワークに足を運んでますが、離職者が増えているのか、【新型コロナウィルス】の影響は大きく、4月末の認定日は、今まで見たこともない程混んでました。
ということで、今回は退職から離職票が届き、失業保険【求職者給付】の受給までを、数年前の経験も含めて、私なりに書いてみました。
失業保険とは?
失業保険(雇用保険)とは、失業した人が失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念し、次の就職先が見つかるまでの生活をサポートするために支給される手当の事です。
一般的に失業手当、失業給付などといわれ【求職者給付】というものです。

求職者給付を受け取るため条件
この【求職者給付】は、退職すれば誰でも受けることができるというわけではありません。
失業保険を受け取るための条件
①原則として離職の日以前2年の間に12ヶ月以上被保険者期間があること。
※被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月後に区切っていた期間に、賃金支払い基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
倒産・解雇等による、離職の場合(特定受給資格者に該当)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他や無負えない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は、離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があること。
②ハローワークにて求職の申し込みを行ない、再就職の意思・能力があり積極的に求職活動を行っているのに就職できない状態であること。
離職から受給まで手続き方法は?
失業保険【求職者給付】は失業したので、すぐにもらえるものではありません。
定められた手続きを行わなければ受給できません。
離職票が届き受給までの手続き方法を必要となるものも含め解説してます。
この時必要な書類があるので、忘れず用意して持っていきましょう。
①雇用保険被保険者離職票
②個人番号確認書類(マイナンバー関連)
③身分証明書(運転免許証など)
④写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
⑤印鑑
⑥本人名義の普通預金口座
私の場合で、早くに就職がしたかった時があって、早くから面接に行き、なかなか就職先が決まらず離職票が送られてきて、ハローワークに受給資格の決定を行いに行き、7日間が経過して、8日目に合格通知が来たことがありましたが、7日間の待期時には、転職活動をしてなかったので、結局最短15日間の無職状態で、すぐに就職し、再就職手当ももらえました!

初回説明会は、各地域で指定された会場で行われます。
受給資格の決定を行った際に渡されたしおりや用紙に記載された持ち物を持って参加しましょう。
初回説明会では、雇用保険受給についての詳しい説明が行われます。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。
ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
支給額
失業保険【求職者給付】は、支給額は、雇用保険の支払い期間(被保険者であった期間)と年齢、過去半年間にもらった給料によって決まります。
過去半年間の給料(賃金)から賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額です。
基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となります。
所定給付日数は以下の通りで、退職理由、年齢、また雇用保険に加入していた期間によって異なります。
| 被保険者であった期間 | |||||
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 (90日※2) | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上40歳未満 | 150日 (90日※2) | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 被保険者であった期間 | |||||
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 全年齢 | − | 90日 | 120日 | 150日 | |
再就職手当もチェック!
再就職手当とは?
雇用保険の受給資格決定を受け、早期に安定した職業に就いた際に一時金を支給する制度です。
ただし、受給するためには、所定(8つ)の支給要件を全て満たす必要があります。
①就職日の前日までの失業の認定を受けた後、基本手当の支給日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
②1年を超えて勤務することが確実であると認められること(契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります)
③待期満了日の就職であること(受給資格の決定から待機期間7日間を満了後)
④離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等のしょうかいにより就職したものであること
⑤離職前の事業者に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等からみて、離職前の事業者と密接な関係にある事業主も含みます)
⑥就職日前3年以内に就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けてないこと
⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた授業主に雇用されたものでないこと
⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
支給額
支給日数×基本手当日額×給付率です。
給付率は、給付率は支給残日数によって違い、残日数が3分の2以上ある場合は70%、3分の1以上3分の2未満の場合は60%とされています。
再就職手当は、支給残日数の支給額の全額貰えるわけではないので、損をする?と考える人もいるのでしょうか?
再就職することで、当然給料がはいります。
給料が入り、再就職手当も貰えるというので、再就職手当は、就職お祝い金なのです。
※私の場合、再就職手当を2回程支給されてます(1度目は平成24年,2度目は平成29年6月)
2回とも認定日前であった事で1回目は60%2回目には70%を受け取りました。

退職の種類について
自己都合退職とは?
自己都合退職した場合に失業保険【求職者給付】を受給するためには、受給資格の決定から、7日間の待期期間を経て、さらに3か月の給付制限期間を経る必要があります。
懲戒解雇(自分の重大なミスによって解雇された場合)は、自分の意思もしくは自分の責任での退職なので、3ヶ月の給付制限期間中は失業保険の支払いが一切されません。
待機期間等+3ヶ月の給付制限期間で、1回目の失業保険の支給日まで約4ヶ月かかります。
自己都合退職に対し、会社の経営破綻や業績悪化に伴う人員整理(いわゆるリストラ)などにより、やむを得ず退職することを会社都合退職と言います。
会社都合退職でよくある理由としては以下のようなものが挙げられます。
会社都合退職とは?
- 会社の経営破綻や業績悪化に伴う人員整理(リストラ)、労働条件が労働契約を結んだときと大きく異なる等で退職することを会社都合退職といいます。
また、賃金の不払いや遅延、セクハラ・パワハラがあったにもかかわらず対策が講じられなかったばあいなども含まれます。
会社都合退職の場合は、自分の意思に反して突然失業となり、生活が困窮してしまう危険性がありますので、7日間の待期期間を経て、その後すぐに支給がスタートし自己都合退職に比べ、優遇措置が受けられます。
特定理由離職者とは?
自己都合退職の退職者でも理由によっては【特定理由離職者】として給付制限が免除される特殊なケースがあります。
会社都合退職と同様に優遇措置を受けられるようになります。
※「特定理由離職者」認められるかどうかは、個別の事例によって異なり、必要書類の提出が求められます。
特定理由離職者の事例
- 契約社員などで有期の雇用契約が満了し、希望しても更新されなかった
- 病気や心身の障害など健康状態が悪化した
- 妊娠・出産・育児などのために離職し、かつ受給期間延長措置(受給期間を最長3年
間延長できる雇用保険法上の手続き)を受けた - 両親の死亡や介護等、家庭の事情が急変した
- 配偶者や親族との別居を続けることが困難になった
- 結婚や事業所の移転などの理由により通勤が困難になった
- 会社からの勧奨があった場合には該当しないが、人員整理等による希望退職者の募
集に応募した

最新情報をお届けします
Twitter でRurikahimeをフォローしよう!
Follow @rurikahime83


















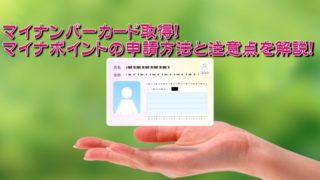










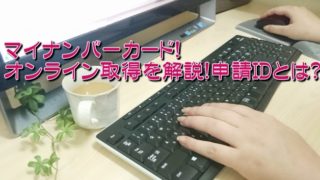









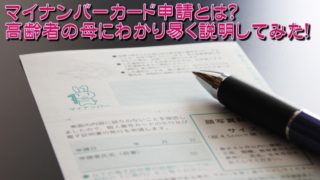






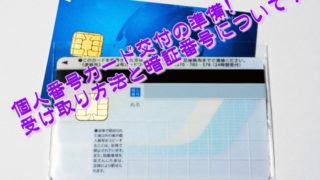

































♡コメント♡ コメントを書き込む♡