去年(令和元年)7月頃、母はかかりつけ医で、心房細動と診断!
血栓ができるのを防ぎ、脳梗塞を予防するお薬(エリキュース)を飲みだしました。
もともと高血圧症、不整脈、脂肪肝、心不全と持病を持っている母(85歳)
同年8月中頃より風邪で、体調を崩し、夜間の異様な咳、全身倦怠感、動機、息切れが続き、食欲は減退し、脈拍は120〜140と頻脈状態へ。
ついた診断は【心房細動の頻脈発作】
全身倦怠感と食欲不振で体重が5kg減っていた母、点滴と頻脈を抑える静注されましたが、数日でまた、再発し、専門医に紹介され、入院が決定!
《カテーテルアブレーション手術》目的で入院をした母、聞いたこともないような手術に不安と、モニター装着、運動制限(トイレ移動のみ)慣れない環境は、高齢の母のには、精神的に辛いものだったのでしょう!
入院生活が半月すぎた頃、心房細動に加え、心房粗動もある事で、医師から説明を受けました。
そこで、今回は心房細動と心房粗動の違いとカテーテルアブレーション手術についてしらべてみました。
心房細動とは?
心房細動の原因と症状
正常な心臓は、心臓内で発生する電気信号によって規則正しい収縮と拡張(拍動)を繰り返しています。
右心房と左心房、右心房と左心室と言う四つの部屋に分かれている心臓、左右の心房は心室に右心室は肺に、左心室は全身に血液を送り出しています。
心房細動は、心臓の左心房(心臓内の部屋)がにある「肺静脈」という血管付近から電気信号が無秩序に生じることでおこります。
心房全体が小刻みに震えて痙攣した状態になると、心拍数が1分間に100〜150回以上になることがあり、心臓が速く不規則に動きます。
うまく働かなくなってしまう心臓の病気(不整脈の一種)です。

心房細動の怖さ!
心房細動自体は、すぐに命にかかわる不整脈ではないのですが、治療をしないで放っておくと、だんだんと発作が頻繁に起こるようになったり、発作の時間が長くなったりしていきます。
加齢にともなって出現しやすい心房細動、また進行しながら状況によっては脳梗塞や心不全など、致命的にもなりかねない重大な合併症を起こす不整脈です。
脳梗塞の種類と原因
心房細動は、心房が小刻みに震えて痙攣している状態なので、血液が滞留しがちになり、心房内で【血栓】(血のかたまり)が形成されることがあります。
血栓が血管を通って脳まで運ばれて脳の血管に詰まると『心原性脳梗塞』と呼ばれる脳梗塞を起こします。
心房細動を起こしている患者と心房細動を起こしてない患者の5倍程度、脳梗塞を発症するリスクが高いと言われています。
心原性脳梗塞は脳梗塞の約3割を占め、心臓で作られた大きめの血栓が詰まることにより引き起こされるため、他の脳梗塞よりも脳のダメージを受ける範囲が広くなります。

ラクナ脳梗塞
主な原因は高血圧
日本人の脳梗塞患者さんでは一番多いタイプで、主な原因は高血圧です。
高血圧で長い間、脳の細い動脈に負担がかかり続けると、血管の壁が厚くなってつまってしまい、脳の深い部分に血が流れなくなってしまいます。
ゆっくりと進行し、症状が出ない場合もあります。
アテローム性脳梗塞
ラクナ梗塞より大きな梗塞巣
主な原因は動脈硬化、血管の壁にコレステロールがこびりついて血管を狭くしてしまうと(動脈硬化)、そこに血栓ができて詰まることで起こります。
脳の比較的太い動脈でも動脈硬化が起こりやすいため、ラクナ梗塞よりも広い範囲に血が流れなくなります。
心原性脳梗塞
軽度なうちは自覚症状がほとんど見られない場合もありますが、症状が落ち着いている状態と急激な悪化を繰り返すこともあります。
心不全は「心房細動」「心筋症」「虚血性心疾患」「心臓弁膜症」など、様々な心疾患が原因でなってしまうといわれていますが、心不全の方が心房細動にかかると、心機能はさらに低下し悪化してしまいます。
例えば、心筋症のひとつである「肥大型心筋症」という病気は、不整脈(心房細動)がないときには症状がありませんが、いったん心房細動による発作を引き起こすと、「急性心不全」を発症し最悪の場合命の危険にさらされてしまうこともあるのです。
現在、心疾患は日本人の死亡原因の第2位であり、心不全と診断されてから5年以内に50%の患者さんが亡くなってしまうという報告もあります。
心不全が悪化するとだんだんと心房細動の発作が頻繁に起こり、発作時間も長く続くことでさらに心不全になりやすくなる、という悪循環に陥ってしまうことがあります。
心房細動と心不全を繰り返す悪循環に陥ってしまう前に、早めに心房細動の治療を受けることが大切です。
心房細動の治療
心房細動がずっと続いていて、止める必要がある場合①抗不整脈薬②電気ショック(電気的除細動といいます)③アブレーション治療―の三つの方法があります。
抗不整脈薬には静脈注射と内服薬があり、この薬剤で心房細動が止まる確率は10~50%と言われています。
薬物療法
血液をサラサラにして脳梗塞を予防するための抗凝固薬と、脈拍を整える抗不整脈薬があります。
抗凝固薬
心房細動のもっとも大きな合併症である脳梗塞を予防するため、血液をサラサラにする抗凝固薬を内服します。脳梗塞を引き起こす可能性の高い場合に内服の適応となり、副作用として出血をしやすくなることがあるため、薬剤管理が重要です。
抗不整脈薬
脈拍を整える抗不整脈薬を内服する目的は、二つに分類されます。
①心房細動を止めて正常な脈に戻すこと
②心房細動は止めずに速い脈を遅くすること
①の目的のためには、心臓の細胞の興奮を抑制するタイプの薬剤が用いられます。
②の目的のためには、交感神経(自律神経の一つで興奮時にはたらく神経)のはたらきを抑制するβ遮断薬や、心房と心室の電気伝導を抑制するカルシウム拮抗薬がよく用いられます。
細胞の興奮を抑える薬剤であるため、副作用として心臓の機能が低下し心不全を起こす可能性や、細胞の興奮が不安定となり重症な不整脈を起こす可能性があります。
抗凝固薬同様、薬剤管理が重要です。
電気ショック
電気ショックは、100ジュール前後の直流電流を一瞬、体に流して不整脈を止める治療法で、ほとんどの心房細動を停止させることができます。
人が集まる施設で見かけるAED(自動体外式除細動器:心臓救命装置)も電気ショックを起こす装置ですが、これは心房細動ではなく、心室細動を止めるために用い、心房細動時の電気ショックの2
倍以上の強力な電気を流します。
心房細動を止める電気ショックでも強い刺激を与えますので、患者さんには、静脈注射で数分~10分ほど眠ってもらい、その間に治療をします。
初めてこれを行う場合は、最低1、2日間入院してもらいます。ただし、何度も電気ショック治療を受けて慣れている患者さんには、日帰りで行うこともあります。
電気ショックは、薬剤を試した後に行いますが、症状のひどい場合は直ちに行うこともあります。ただし、心房細動をなくす根本的な治療法でないため、これで心房細動が止まったとしても、すぐ(数秒~数時間内に)再発する人がいます。
数か月以内に再発した場合、再度電気ショックをしても効果は期待できませんので、アブレーションが次の治療の第一選択肢となります。
電気ショックでは1%前後の人が脳梗塞を発症する可能性がありますので、受ける前と後の3週間以上にわたって抗凝固薬を飲む必要があります。できれば受ける前に、食道に超音波内視鏡を入れる「食道エコー検査」で、心房に血栓のないことを確かめた方がよいとされています。

8月に風邪が原因で、不整脈が悪化、全身倦怠感、頻脈で10月入院、カテーテルアブレーション手術前の処置【電気ショック】施行をする目的で入院。入院と同時にエリキュースから、ワーファリンに変更し、3週間後電気ショックを施行。電気ショック施行後、正常な脈に戻ったが、2時間後には心房細動になり、また頻脈へ。電気ショック施行前、新たに【心房粗動】もあるとの事!根治療法のカテーテルアブレーション手術は、先生曰く、2時間でも正常な脈になったので、手術は可能だということでしたが、母の場合もう一つ問題が!入院後【せん妄】が日に日に悪化していることです。また認知症とも取れる言動が増えてきて、アブレーション手術を行うには、少し難しいと言われました。
カテーテルアブレーション手術(治療)
心房細動は大きく分けると
①発作性心房細動(1週間以内に治まる)
②持続性心房細動(1週間以上持続する)
③長期持続性心房細動(1年以上持続する)
④永続性心房細動(永久に改善しない)
と分けられ、①~④へと進行していき、永続性心房細動に近づくほど、カテーテルアブレーション手術はを行っても治療効果が、悪かったり、再発しすかったりすると言われています。
カテーテルアブレーション手術は、できるだけ早期の「発作性心房細動」の段階で行うことが理想的です。
しかしながら、発作性心房細動であっても、動悸や胸部不快感などの自覚症状に気づかない患者さんもいらっしゃり、診断時にはすでに持続性や長期持続性の心房細動となっている患者さんも少なくありません。
食事療法で塩分制限も大事です。
🍅簡単・時短調理で制限食事!管理栄養士監修の制限食料理キット
心房粗動とは?
心房細動は、心臓の左心房(心臓内の部屋)がにある「肺静脈」という血管付近から電気信号が無秩序に生じることでおこり不整脈ですが、次は心房粗動についてしらべてみました。
心房粗動の原因と症状
粗動は1分間に250~320回くらいの頻度で興奮(収縮)します。
しかし、電気信号が心房と心室をつなぐ「房室結節」を通過するときに、興奮が伝わったり伝わらなかったりすることがあります。そのため心拍数は早くなったり遅くなったりします。
症状は、動機や失神などがありますが、場合によっては無症状のこともあります。
症状の有無は、房室結節が伝道しやすいか、伝道しにくいかで決まります。
例えば粗動が1分間に240で収縮していて、2回に1回が心室に伝わると240÷2=120回/分となrので、心拍数が速くなり動悸を訴えることがあります。
しかし、3回に1回や、4回に1回の電動であれば、80回/分や60回/分となって症状が出にくくなり無症状となることがあります。
一方で1分間に240回全てが房室結節伝道してしまうと寝室の興奮が240回/分となり、心拍数が速くなりすぎてしまい、心臓の拡張時間が短くなり、十分な血液を 心臓に蓄えることができません。
その結果必要な血液を心臓からですことができなくなり、血圧が低下し、失神することもあります。
心房粗動は、命にかかわる危険な状態になる可能性もある疾患です。
心房粗動では、心房の壁がブルブルと速く震えるように興奮するため、血液が心房内によどんでしまう事があり、心房の中に、血液のかたまり(血栓)ができてしまうことがあるのです。
できてしまった血栓は心臓の収縮によって、押し出され、血液とともに脳へと移動し、様々な臓器の血管で詰まってしまうことがあります。
その中でも脳の血管で詰まり《脳梗塞》を起こすと、極めて重症となって、命に拘る危険な状態となります。
また、心房粗動で心拍数が異常に速くなることで失神するというのは《突然死》の前段階の可能性もあります。
心房粗動が見つかった場合、自覚症状はなくても、突然死を招く可能性があり、治療を積極的に検討することをお勧めします。
「心房粗動」と「心房細動」の違いは?
《心房細動》と《心房粗動》どちらも頻脈性(脈が速くなる)の不整脈で似た症状ですがどんな違いがあるのか?調べてみました。
電気信号の旋回の仕方が異なる
心房粗動と心房細動は、電気のループ(繰り返し)が心房の中にあるという点は共通しているので、病態は非常に似ています。
心房粗動の場合は、旋回する電気ループがひとつで、同じところをぐるぐる回っています。
それに対して、心房細動は小さな電気ループが6~8個程度心房内に同時にでき、それらのループが動き回って一定の場所にとどまっていない状態になります。
心房細動は、小さな電気ループなので、1分間に400~600回というスピードで回っていますが、早すぎて房室結節の伝導が追従できず、心房:心室の伝導が1:1伝導になることはないと考えられます。
そのため心房粗動と異なり、失神や突然死につながる頻拍になりにくいという特徴があります。
心房粗動→大きなループが一つ
心房細動→小さいループがたくさん
 また、心房細動と心房粗動では『ループの回転する速さ』も違いがあります。
また、心房細動と心房粗動では『ループの回転する速さ』も違いがあります。
心房細動では1分間に約400〜600回の回転
心房粗動では1分間に約250〜320回
また心房粗動と心房細動では「ループの回転する速さ」も異なります。
心房粗動と心房細動と似たような不整脈に「頻拍(ひんぱく)」と呼ばれる状態があります。
「頻拍」と「粗動」と「細動」の区別は、発生メカニズムや解剖学的な違いでも分類されますが、最もわかりやすい分類は、頻度ではないでしょうか。つまりそれぞれ1分間あたりにどれくらいの電気信号が回転しているかによって分類するものです。
心房細動では1分間に約400~600回の回転で、とても速いです。心房粗動では1分間に約250~320回で、心房細動と比べるとゆっくりになります。また、心房粗動よりも電気信号の回転がゆっくりな「頻拍」では、1分間に約120~250回になります。
このように、電気信号のループの回転の速さによっても、心房粗動と心房細動には違いがあることがわかるでしょう。こうした回転の速さの違いは、電気ループの大きさによるものと考えられています。

心房粗動の治療方法は?
心房粗動の頻脈の処置
薬物療法と電気ショックの処置があります。
薬物療法
頻脈を抑えるための処置として、β遮断薬やカルシウム拮抗薬といった薬剤を使い心拍数の調整に使用されます。
また、ナトリウム遮断薬やカリウム遮断薬によって、旋回(ループ)そのものを止めたり、心房粗動が出たり引っ込んだりする場合には、起こり始めの期外収縮を抑えて粗動にならないようにする目的で使われることもあります。
しかし、心房粗動は突然死をきたす可能性がある事、抗不整脈薬の長期内服は心機能低下を引き起こすことがあるので、根治療法のカテーテルアブレーション手術の検討も大切です。
これらの薬剤は、房室結節に作用して心房から心室に伝導しにくくなり、心室に伝わる電気信号の数を減らすことができるという機序をもっています。
こうした薬剤を服薬することは動悸の症状を軽減することにつながります。
電気ショック
緊急で頻脈を止めなくてはならないときには電気ショック療法を行う場合があります。
薬剤による治療は、服薬してから効果があらわれるまでの時間を要するため、緊急性の高い場合には電気ショックを与え、異常に興奮した電気信号のループを止めていきます。
また、薬剤による治療は心筋の異常な収縮を抑えるぶん、心臓全体の機能を低下させることになるため、心不全をおこしている可能性がある場合には、そうした機序を持つ薬剤の使用がリスクとなる場合があります。
その場合には薬物療法ではなく、電気ショック療法を行うことになります。
心房粗動の根治療法
カテーテルアブレーション手術(治療)
頻脈の処置として、薬物療法と電気ショックがありますが、根治療法のカテーテルアブレーション手術(治療)の説明です。
心房細動では、いくつかのループが旋回している為、アブレーションが困難な場合があるのに対し、心房粗動の場合、一つの大きなループで巡回している為、そこを焼灼すれば根治できる可能性が高いと言えます。
どのような方法?
カテーテルアブレーション手術(治療)とは、先端に治療や検査を行うための機能をつけ、カテーテル(医療用の細い管)を、足の付け根の血管から挿入して、心臓の治療をする方法です。
挿入されたカテーテルを心臓に到達させたあと、心臓の状態を調べつつ、病変を確認。
原因の部分が明らかになったら、異常な電気興奮を遮断できるように、原因となっている部分を通電を加えて焼灼します。
※心房粗動のガイドラインでも【有症状の場合はもちろんのこと、とくに心室機能低下を伴う場合などでは無症状であっても積極的に適応を検討する】と記載があり、カテーテルアブレーション手術(治療)は、心房粗動の治療において、重要な資料選択技であると考えられる。
心房粗動は突然死のリスクも考えられるものですが、カテーテルアブレーション手術(治療)で根治できる疾患です。
今年の1月に入り、状態は悪化!体重も退院後5㎏の増加
脈拍が140/分と頻脈時に飲む薬(ワソラン)も飲んでも効果なく、心臓に負担が増していくばかりで、浮腫が酷くなり、病院受診。
浮腫みを減らすお薬を処方して頂き、余り飲ませてはなかったのですがワソランは中止!
カテーテルアブレーション手術(治療)の紹介状を書いていただきました。
1月末受診しました。
アブレーション手術は現在、手術が3か月待ちの状態でしたが母の場合、状態が酷く2月半ばにアブレーション手術施行がほぼ決定!
手術前に2月に入り、心臓のCTを撮りに受診したのですが…
ちょっと違う展開になりました!
最新情報をお届けします
Twitter でRurikahimeをフォローしよう!
Follow @rurikahime83















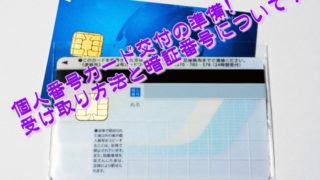
























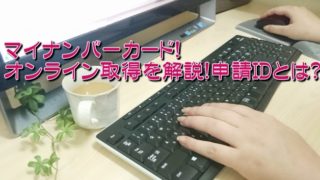









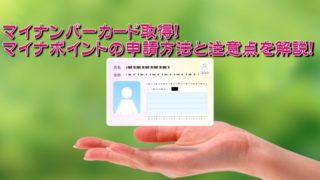




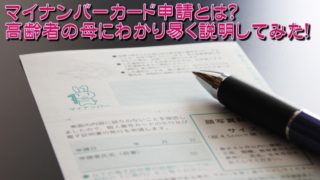



























♡コメント♡ コメントを書き込む♡